その道に入らんと思う心こそ 我身ながらの師匠なりけれ
意味
「何かの道(茶道など)に入ろうと思う、その気持ちこそが、自分自身にとって最大の師匠となる」という意味です。
解説
千利休はこの和歌を通じて、「学ぶ姿勢」そのものの大切さを説いています。どんな分野であっても、外から与えられる知識や技術だけではなく、「自ら学びたい」「上達したい」という気持ちが最も重要な要素となります。
ポイント
- 学ぶ姿勢がすべての出発点
- どんな優れた師匠についても、自分自身に「学びたい」という心がなければ成長はない。
- 逆に、その気持ちさえあれば、たとえ独学であっても成長できる。
- 外からの教えよりも、自分の内なる意志が大切
- 他人に教えを乞うことは大切だが、最も頼るべきは「自分の向上心」。
- 何事も「やらされる」より「自ら進んでやる」ほうが身につきやすい。
- 茶道だけでなく、すべての学びに通じる教え
- この考え方は茶道だけでなく、武道、芸術、ビジネス、学問など、あらゆる分野に当てはまる。
- 英語や資格試験等についても、学びたいと思う気持ちが最も重要。
この和歌は、「学びの本質は外ではなく、自分の心の中にある」という利休の哲学を端的に表しています。
古典文法 ワンポイント
その道に 入らんと思う 心こそ 我が身ながらの 師匠なりけれ
- 文法: 係助詞「こそ」
- 解説: 「こそ」は強調のための係助詞であり、結びの部分に影響を与えます。
- 係助詞「こそ」が使われると、文末の活用形が「已然形」になる(係り結び)。
- ここでは、「なりけれ(已然形)」と結ばれている。
びゅ~も と 和歌
入門した初日に、先生から教わった最初の和歌です。
現代では茶道を習っている人は女性が多く、男性は少ないです。
でも茶道は前々から興味があり、そこに茶道の市民講座があるのをみつけ習いはじめました。
男性が茶道を習うのはハードルが高い(と思っていた)中、受講を決めて良かったと思っています。
余談ですが昔は男性が多く、明治以降に女性が増えました。
まとめ
この和歌は、「学ぶ意欲こそが最大の師匠である」というメッセージを持っています。
社会人・学生・趣味・人間関係・人生観 など、あらゆる場面で役立ちます。
この和歌から学べること
- 「やらされる」のではなく「自ら学ぶ」ことが大事。
- 「学びたい!」という気持ちがあれば、どこでも成長できる。
- 環境に左右されず、自分の意志で進むことが、人生を豊かにする。
この考え方を持つだけで、勉強や仕事、人間関係など、どんな場面でも前向きに生きる力になります。
rapで利休百首
タイトル:「俺の師匠は俺の心」 🎤🎶
(1) その道に 行くぜ決めたらブレない
(2) 迷うヒマねえぜ 自分が師匠さ 絶対
(3) 型を学んで 次に破るルール
(4) でも大事なのは 内に燃えるツール
(5) 押しつけられたら それは意味ねえ
(6) 俺がやりてぇ それが本音
(7) 茶を点てるだけ? いや違ぇよ
(8) 心が決める 俺の流儀よ
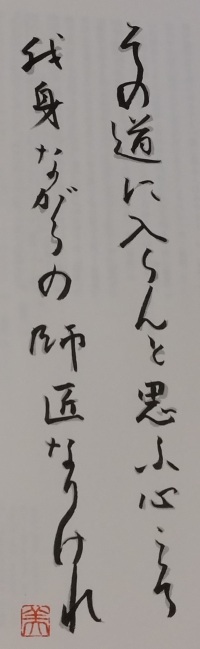

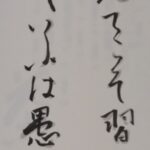
コメント